
弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
第一東京弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
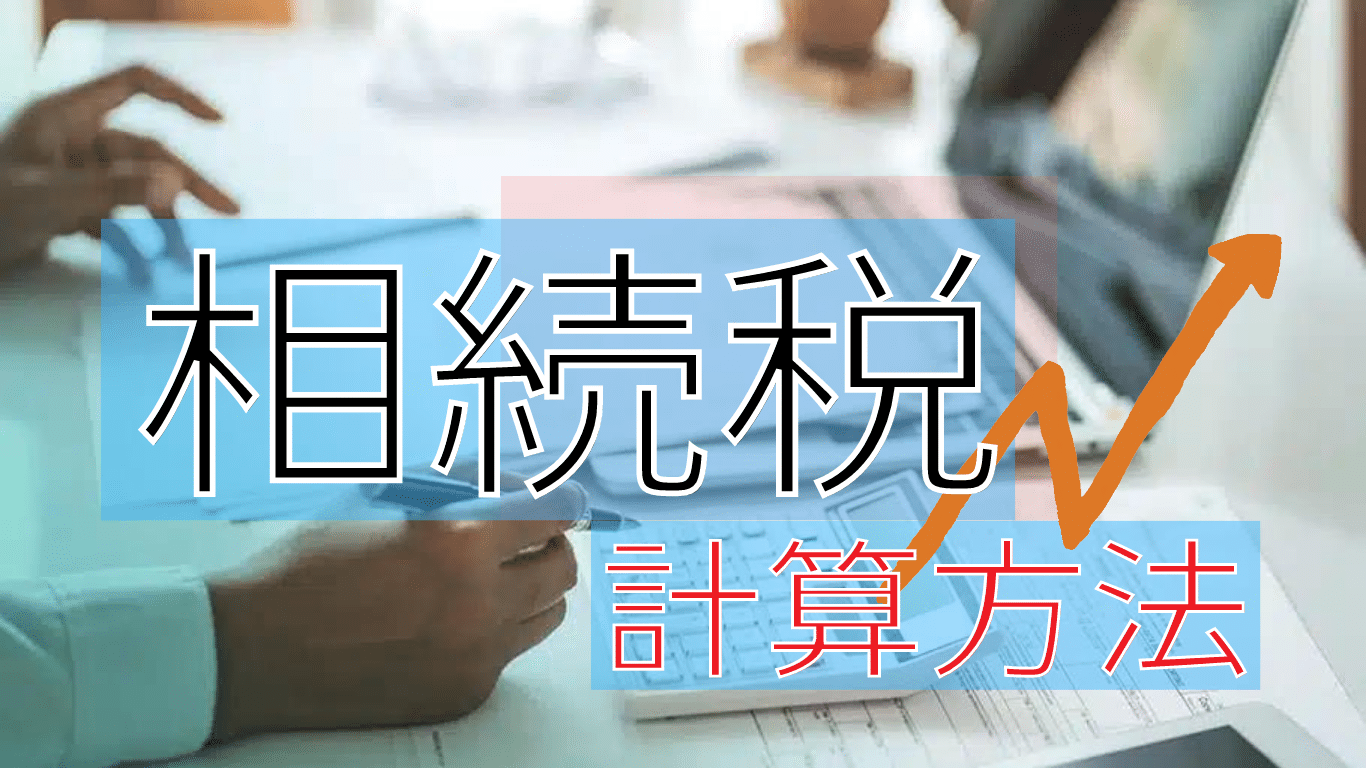

弁護士 西村 学
弁護士法人サリュ代表弁護士
第一東京弁護士会所属
関西学院大学法学部卒業
同志社大学法科大学院客員教授
弁護士法人サリュは、全国に事務所を設置している法律事務所です。業界でいち早く無料法律相談を開始し、弁護士を身近な存在として感じていただくために様々なサービスを展開してきました。サリュは、遺産相続トラブルの交渉業務、調停・訴訟業務などの民事・家事分野に注力しています。遺産相続トラブルにお困りでしたら、当事務所の無料相談をご利用ください。
親族が急に亡くなり、相続が開始すると、避けて通ることができないのは相続税の申告です。人によっては申告が不要な場合もありますので、早い段階で確認しておきましょう。
本記事を読むことで、
がわかります。ぜひご覧ください。
なお、弁護士法人サリュには相続税に詳しい弁護士や税理士登録している弁護士も在籍しておりますので、とにかく相続税について相談したいという方は、弁護士法人サリュの無料相談をご利用ください。
まず、課税価格(遺産の額)から基礎控除額をマイナスした課税遺産総額を計算しましょう。もし、課税遺産総額が、基礎控除によって、ゼロになるのであれば、相続税の申告は不要です。
遺産の額から、債務や葬式費用を控除したものが、課税価格です(相続税法11条の2、13条)。例えば、不動産3000万円、預貯金が2000万円で、葬儀費用が200万円の場合、
(不動産3000万円+預貯金2000万円)−葬儀費用200万円=4800万円
で、課税価格は4800万円となります。
基礎控除額は、3000万+(600万×法定相続人の人数)によって計算します。例えば、相続人が配偶者のみであれば、3600万円が基礎控除額となります(相続税法15条1項)。相続人が配偶者のほか、子供2人であれば、4800万円となります。
もし、上記の例のとおりの遺産で、相続人が配偶者のみの場合は、
課税価格4800万円-基礎控除額3600万円
=課税遺産総額1200万円
となります。
次に、課税遺産総額を法定相続分で按分し、その金額をもとに相続税を計算します(相続税法16条)。上記の例で法定相続人が配偶者のみであれば、1200万円について、速算表を適用して計算します。
相続税の税率、速算表は国税庁のHPから
3000万円以下の場合、15パーセントの税率に、50万円の控除がありますので、
1200万円×0.15-50万
=130万円
となります。
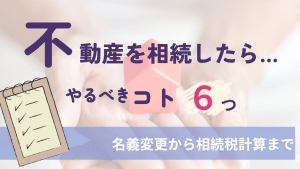

配偶者には大きな減税制度があります。配偶者が取得した遺産額が1億6000万円に満たない場合には相続税はないものとする税額軽減があります(相続税法19条の2)。
上記の例の場合、相続税を納める必要はありません。
なお、配偶者の税額軽減を受けることができる場合にも、相続税の申告書を提出しなければなりませんので注意が必要です。
相続税については、種々の軽減制度が用意されており、相続税を意識した遺産分割協議が重要となります。相続税や遺産分割協議についてお困りのことがあれば、当事務所の無料相談をご利用ください。
